
妊娠7ヶ月で出産準備を始めるのは早いのかな?と迷っている方は多いですよね。
この記事では「出産準備 7ヶ月 早い」という疑問に答えながら、7ヶ月で準備を始めるメリット・デメリット、必需品リスト、そして8ヶ月以降でも間に合うものまで詳しく解説します。
先輩ママのリアルな体験談も交えているので、「どこまで準備しておけば安心なのか」がイメージできるはずです。
出産に向けて不安や焦りを減らし、安心して赤ちゃんを迎えられるように、一緒に準備のタイミングを確認していきましょう。
出産準備は7ヶ月から始めても早くない?
出産準備は7ヶ月から始めても早くない?について解説します。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
①7ヶ月は安定期後で動きやすい時期
妊娠7ヶ月といえば、安定期を過ぎて体調も比較的落ち着いている人が多い時期です。お腹はだんだん大きくなってきますが、まだ歩いたり買い物に出かけたりできる余裕がある方も多いです。そのため、重い荷物を持ったり店頭で実物を見て選んだりといった動きが可能なうちに準備を進めておくのは合理的なんですよね。
特にベビーベッドやベビーカーなど、大きめの育児グッズはネット注文しても配送・組み立てに時間がかかる場合があります。7ヶ月の段階で注文しておくと、体調が落ち着いているうちに設置できて安心です。あとになって「体が思うように動かせないのにまだ準備が終わってない!」となると、心身ともに負担になってしまいますからね。
実際、先輩ママの声を見ても「7ヶ月である程度準備しておいて正解だった」という意見は多いです。体調が安定している時期だからこそ、動けるうちに買い物を済ませるのはとても合理的な判断だといえるでしょう。
私自身も、重いオムツのまとめ買いやチャイルドシートの受け取りは7ヶ月ごろに済ませておいて本当に良かったと思いました。動けるうちにやる!これがポイントですね。

②体調や入院リスクを考えると安心
妊娠後期に近づくと、切迫早産などのリスクが出てきたり、突然の入院になるケースもあります。そのため「まだ先だから大丈夫」と思っていたら、急に入院になって出産準備がほとんどできていなかった…という人も少なくありません。
7ヶ月の段階で最低限の準備を進めておくと、もしものときも安心です。特に入院バッグや赤ちゃんの肌着、退院時に必要なグッズなどは早めに揃えておいて損はありません。実際、病院からも「臨月に入る前には入院準備をしておいてください」と案内されることが多いです。
精神的にも「準備ができている」という安心感は大きな支えになりますよね。出産を控える妊婦さんにとって、不安や焦りを減らすことはとても大切です。7ヶ月で準備を始めることは、その意味でも心強い行動といえます。
私も友人から「急に切迫早産で入院したけど、7ヶ月で準備していたから大丈夫だった!」という話を聞きました。体調やリスクを考えると、やっぱり早めに動くのは正解なんですよね。
③必要なグッズをじっくり選べる
出産準備は、単に必要なものを揃えるだけではなく「どの商品を選ぶか」も大事です。ベビー用品は種類が豊富で、メーカーごとに特徴や価格も違います。口コミを調べたり、実物を見比べたりして選ぶには時間が必要です。
7ヶ月から準備を始めれば、焦らずじっくり比較検討できます。たとえば抱っこ紐ひとつとっても、新生児から使えるものや腰の負担が少ないものなどいろんな選択肢があります。ネットでレビューを読みながら選ぶ時間を持てるのは、早めに準備を始める大きなメリットです。
また、セールやキャンペーンを狙う余裕もできます。必要なものをリストアップしておけば、タイミングを見計らってお得に購入することも可能です。7ヶ月から始めれば「じっくり選んで節約できた」というケースも少なくありません。
個人的には、抱っこ紐とベビーベッドは時間をかけて選んで本当に良かったです。7ヶ月くらいから調べ始めて比較検討し、納得いくものを買えたので、使うときも満足度が高かったですね。
④夫婦で相談する余裕がある
出産準備はママひとりで進めるものではなく、夫婦で一緒に考えることが大切です。特にベビーカーやチャイルドシートなどは、使う場面を夫婦でシミュレーションして選んだ方が失敗が少なくなります。7ヶ月のうちに始めれば、週末にゆっくり買い物に行ったり話し合ったりする余裕があります。
また、パパにとっても「自分も一緒に出産準備をしている」という感覚は、出産や育児に対する意識を高めるきっかけになります。ママが後期に入り体調がきつくなってからだと、相談する余裕もなく「とりあえず必要だから買った」という流れになりがちです。
7ヶ月から準備を始めれば、夫婦でじっくり意見交換できるので、満足度の高い買い物ができますし、出産に向けた気持ちの準備にもつながります。私の知り合いも「7ヶ月で準備を始めて、夫婦でベビーカーを見に行ったのがいい思い出になった」と話していました。
一緒に考える時間を持てるのも、7ヶ月から始める大きなメリットですよ。
出産準備を7ヶ月に始めるメリット4つ
出産準備を7ヶ月に始めるメリット4つについて解説します。
それぞれのメリットを、詳しく掘り下げていきますね。
①時間に余裕を持って揃えられる
妊娠7ヶ月から準備を始める大きなメリットは、何といっても「時間に余裕がある」ということです。妊娠後期に入ると、お腹が大きくなり動きが制限されますし、体力的にも買い物や調べものが負担に感じやすくなります。その点、7ヶ月の段階なら体調も比較的安定していて、買い物やネット注文を落ち着いて進められるのです。
また、赤ちゃん用品は思った以上に種類が多く、すぐに決められないことも多いです。哺乳瓶ひとつとっても、メーカーやサイズ、材質などで迷うポイントがたくさんあります。そうした選択肢を比較しながら、じっくり納得のいく買い物をするには、やはり時間が必要なんですよね。
7ヶ月から準備を始めておけば、リストを作って計画的に揃えられるので、後から「あれも買わなきゃ!」と焦ることが少なくなります。精神的にも余裕を持って行動できるのが大きなメリットです。
私自身も、出産準備の際に「ベビーベッドをどれにするか」で数週間悩みました。7ヶ月から探し始めたおかげで、焦らず比較できて、最終的に満足できるものを選べたのは大正解でした。
②急な入院や早産に備えられる
妊娠後期は、思わぬ体調の変化や切迫早産などで、急に入院を余儀なくされることもあります。実際に「臨月までに準備すればいいや」と思っていた人が、入院になってほとんど用意できなかった、という話も珍しくありません。
7ヶ月のうちに最低限の出産準備を整えておけば、そうした予期せぬ事態にも対応できます。特に「入院バッグの中身」や「赤ちゃんが生まれてすぐ必要なもの」は、早めに揃えておくと安心です。例えば、肌着やガーゼ、オムツなどは必須アイテムなので、7ヶ月からでも準備しておくべきですね。
実際に病院でも「出産の1か月以上前には入院バッグを準備しておいてください」と案内されることが多いです。7ヶ月から準備を始めることで、もしもの事態に落ち着いて対応できるのは、大きな安心材料になります。
私の友人も、妊娠8ヶ月で切迫早産のために緊急入院しましたが、7ヶ月のうちに最低限の準備をしていたおかげで慌てずに済んだそうです。やはり早めの準備は安心につながりますよね。
③セールやキャンペーンを利用できる
出産準備は、揃えるアイテムが多いぶん費用もかさみます。そのため「いかにお得に揃えるか」がとても大切なんです。7ヶ月から準備を始めれば、必要なものをリストアップしておき、セールやキャンペーンのタイミングを狙って購入することができます。
例えば、ベビー用品店やネットショップでは定期的にセールが開催されていますし、出産準備フェアのようなイベントもよくあります。ベビーカーや抱っこ紐、ベビーベッドなど高額なアイテムを安く購入できるチャンスを逃さずに済むのは、7ヶ月から準備する大きなメリットです。
さらに、出産予定月に合わせたプレゼントキャンペーンやポイント還元を活用できるのも魅力です。時間に余裕があるからこそ、価格や特典を比較してお得に準備を進められるんですよね。
私は7ヶ月のときに「大型ベビー用品10%オフセール」を狙ってまとめ買いしました。数万円単位でお得になったので、本当に早めに動いてよかったと感じましたよ。
④心の安心感が得られる
出産に向けた準備が整っていると、「ちゃんと準備できているから大丈夫」という安心感を得られます。これは精神的にとても大きなメリットです。妊娠中は体調やホルモンの影響で不安を感じやすくなるものですが、準備を進めておくことで気持ちが安定しやすくなります。
逆に「まだ準備していない」という状態が続くと、頭の片隅で常に焦りや不安を感じてしまいがちです。そのストレスは妊婦さんにとって良くありませんし、出産に向けた前向きな気持ちを持ちにくくなってしまいます。
7ヶ月のうちに準備を始めることで、少しずつ「これで安心」という気持ちを積み重ねていけるのは、精神的にもとても心強いです。気持ちに余裕があると、赤ちゃんを迎える楽しみをじっくり味わうこともできますよね。
私自身も、ベビー服を揃えていく過程で「赤ちゃんがもうすぐ来るんだな」と実感できて、とても幸せな気持ちになりました。心の準備を整えるという意味でも、早めの出産準備はメリットが大きいですよ。
出産準備を7ヶ月に始めるデメリット3つ
出産準備を7ヶ月に始めるデメリット3つについて解説します。
メリットが多い一方で、早めに準備を始めることで起こりやすい注意点もあります。それぞれ見ていきましょう。
①買いすぎや無駄な出費のリスク
7ヶ月の段階で出産準備を始めると、「赤ちゃんを迎える楽しみ」が先走ってしまい、つい買いすぎてしまうことがあります。小さなベビー服や便利そうなグッズを見ていると、どれも欲しくなってしまうのは自然なことですよね。ただし、赤ちゃんは成長がとても早いため、サイズアウトして着られない服が出たり、結局使わなかったグッズが残ってしまうことも多いです。
例えば「新生児用の服を大量に買ったけど、2週間でサイズが合わなくなった」とか「便利そうだと思って買ったけど、実際には一度も使わなかった」という話は先輩ママからもよく聞きます。特に7ヶ月で準備を始めると、まだ実際の生活がイメージしづらく、本当に必要かどうか判断がつきにくいんですよね。
このデメリットを避けるためには、「最低限必要なものから揃える」ことがポイントです。肌着やオムツなど絶対に必要なものに絞って買い揃え、便利グッズやおしゃれ着は出産後に必要に応じて買い足す、というスタンスが無駄を防ぐコツですよ。
私自身も、最初は可愛いベビー服をたくさん買いたくなりましたが、先輩ママに「結局ほとんど着ないよ」と言われ、ぐっと我慢しました。その結果、無駄な出費を防げて本当に良かったと思っています。
②季節に合わないグッズを選んでしまう
7ヶ月で準備を始めると、実際に赤ちゃんが生まれる季節を見越してアイテムを選ばなければなりません。例えば冬生まれの赤ちゃんに夏用の薄着を揃えてしまったり、夏生まれなのに厚手の服を用意してしまったりと、季節に合わない準備をしてしまうリスクがあるのです。
特にベビー服や寝具は季節感が大きく影響します。赤ちゃんは体温調整が未熟なので、季節に合った服装や寝具が必要になります。7ヶ月の時点では「まだまだ先だから」とイメージしづらいですが、出産予定の季節に合わせて準備することを意識しないと、無駄になってしまうことがあります。
対策としては、洋服や布団など季節に左右されやすいアイテムは最低限にとどめ、出産直前や出産後に実際の気候を見て買い足すのがおすすめです。例えば肌着や基本的な寝具だけ用意して、毛布や防寒グッズは必要になってから揃える、といった工夫が有効です。
私の知人は、夏生まれの赤ちゃんに冬物を用意してしまい、結局使わずに新品のままリサイクルに出すことになったそうです。こうした失敗を避けるためにも、季節をしっかり考えて準備したいですね。
③後期に必要性が変わる可能性
妊娠後期になると、病院からの指導や赤ちゃんの発育状況によって「必要なもの」が変わることがあります。例えば母乳育児を予定していたけれど、思うように軌道に乗らず哺乳瓶が必要になったり、予定外の入院が増えて消耗品が多く必要になったりするケースです。
7ヶ月で一気に買い揃えてしまうと、こうした変化に対応しづらくなるのがデメリットです。実際に「必要だと思って早めに買ったけど、使わなかった」という声は多く、結果的に無駄になってしまうことも少なくありません。
このリスクを避けるには、「必要最低限+様子を見て買い足す」というスタイルが一番安心です。大きな家具や必需品は早めに揃えても大丈夫ですが、細かいグッズや数量が決まっていないものは後回しにするのが安全です。
私も、7ヶ月のときに「粉ミルクや哺乳瓶は必須」と思って買っていましたが、結果的に完全母乳でほとんど使わず終わりました。今なら「最低限で十分」と言えますね。状況が変わる可能性を踏まえて準備するのが大切です。
妊娠7ヶ月で揃えておきたい必需品リスト
妊娠7ヶ月で揃えておきたい必需品リストについて解説します。
ここでは、7ヶ月のうちに揃えておくと安心なグッズをカテゴリー別に紹介していきます。
①赤ちゃんのお世話グッズ
まず揃えておきたいのは、赤ちゃんが生まれてすぐに必要になるお世話グッズです。特に肌着やオムツ、ガーゼなどは必需品なので、7ヶ月のうちに準備しておくと安心です。赤ちゃんは思った以上に汗をかきますし、ミルクの吐き戻しも多いため、着替えやガーゼは多めに用意しておくと便利ですよ。
また、ベビー布団やおくるみも必要になります。おくるみは退院時にも使えますし、寝かしつけや抱っこのときにも役立つ万能アイテムです。さらに哺乳瓶や消毒グッズなど、授乳に関するものも準備しておくと安心です。母乳育児を考えている方でも、哺乳瓶を1〜2本は持っておくと、万が一のときに便利ですよ。
代表的なお世話グッズを表にまとめました。
| アイテム | 目安量 | ポイント |
|---|---|---|
| 短肌着・長肌着 | 各3〜5枚 | 季節に応じて調整。肌に優しい綿素材が安心。 |
| ガーゼハンカチ | 10枚以上 | 授乳時や吐き戻しで頻繁に使用。 |
| おむつ | 新生児用1パック〜 | まとめ買いはせず、まずは少量で試す。 |
| おくるみ | 1〜2枚 | 退院時にも使用可能。季節に合った素材を。 |
| ベビー布団セット | 1組 | 掛け布団は軽め、敷布団は硬めが基本。 |
私の場合、特にガーゼは「いくらあっても足りない!」と感じるくらい重宝しました。洗い替えを考えて多めに準備するのがおすすめです。

②入院・出産に必要なもの
次に重要なのが、入院・出産に必要なものです。これは病院によって多少異なるので、病院からもらうチェックリストを必ず確認してください。ただ、共通して必要になるアイテムも多いので、7ヶ月のうちに少しずつバッグに詰めておくと安心です。
代表的なものとしては、産褥ショーツや授乳用ブラジャー、母子手帳、スリッパ、タオル、退院時に着るベビー服などがあります。特に「入院バッグ」と「陣痛バッグ」の2種類に分けて用意しておくと、必要なタイミングですぐ取り出せて便利です。
以下に、入院準備の代表的なアイテムを表にまとめます。
| アイテム | 用途 | ポイント |
|---|---|---|
| 母子手帳・保険証 | 入院手続き | すぐに取り出せる場所に入れておく。 |
| 産褥ショーツ | 産後すぐ使用 | 2〜3枚用意しておくと安心。 |
| 授乳用ブラ | 入院中〜退院後 | 締め付けのないものを選ぶ。 |
| フェイスタオル | 洗顔・授乳時 | 清潔なものを3〜4枚。 |
| ベビー退院服 | 退院時 | 肌着+カバーオールでOK。季節に合わせる。 |
私は7ヶ月の時点で「入院バッグ」を玄関に置いておきました。急に入院が必要になったときでも安心できたので、かなり心の余裕につながりましたよ。
③ママの産後ケア用品
赤ちゃんの準備だけでなく、ママの産後ケア用品も早めに揃えておくと安心です。産後は体の回復が優先で、買い物に出るのは難しいため、あらかじめ必要なアイテムを準備しておくことをおすすめします。
例えば、産褥パッドや授乳クッション、円座クッション、骨盤ベルトなどが役立ちます。母乳パッドも必須アイテムで、入院中から使用するケースが多いです。これらは7ヶ月のうちに買っておいても無駄になりにくいので、先に用意しておくと安心ですよ。
私のおすすめは授乳クッションです。授乳時の姿勢を楽にしてくれるので、肩や腰への負担が軽くなります。授乳期が終わっても、赤ちゃんのお座りサポートや大人の昼寝用枕としても活用できるので、長く使えるアイテムですよ。
④最低限これだけは揃えておく物
最後に「7ヶ月で最低限これだけは揃えておくと安心」というアイテムをまとめます。すべてを完璧に揃える必要はありませんが、このリストがあると安心して出産に臨めます。
- 短肌着・長肌着(季節に合わせて)
- おむつ・おしりふき
- ガーゼハンカチ
- おくるみ
- 母子手帳・保険証(入院時)
- 産褥ショーツ・授乳ブラ
- 退院用ベビー服
これだけ揃えておけば、いざ赤ちゃんが早めに生まれても慌てずに対応できます。その他のグッズは、出産後に必要に応じて買い足すスタイルでも十分間に合いますよ。

出産準備は8ヶ月以降でも間に合うもの
出産準備は8ヶ月以降でも間に合うものについて解説します。
7ヶ月で最低限の必需品を揃えておけば、残りは8ヶ月以降でも十分に間に合います。焦らなくてもいいアイテムを順番に見ていきましょう。
①季節ごとの服や小物
赤ちゃんの洋服は、出産の季節やその後の気候によって必要なものが変わります。そのため、7ヶ月の段階で全てを揃える必要はありません。むしろ出産直前や出産後に気候を見ながら揃えた方が失敗が少ないんです。
例えば、冬生まれの赤ちゃんなら厚手のカバーオールや防寒用おくるみが必要になりますが、春先や秋なら薄手で十分な場合もあります。逆に夏生まれなら通気性の良いロンパースやガーゼケットが活躍します。
また、靴下や帽子などの小物類も季節に合わせて購入すればOKです。7ヶ月の時点では最低限の肌着だけにして、8ヶ月以降に気候を見ながら追加するスタイルが賢いですよ。
私は冬生まれの子を出産しましたが、7ヶ月の段階で夏物セールに飛びついて薄手の服を買ったのは完全に無駄になりました…。その経験からも、季節物はギリギリまで待つのがおすすめです。
②消耗品や買い足しグッズ
オムツやおしりふき、母乳パッドなどの消耗品は、ストックしておくと安心ですが、最初から大量に買う必要はありません。むしろ赤ちゃんによって肌に合うオムツの種類が違ったり、ママによって母乳パッドの使用量が変わったりするため、必要に応じて買い足す方が効率的です。
哺乳瓶の乳首サイズや粉ミルクも、出産後の授乳スタイルが定まってから揃えた方が無駄がありません。7ヶ月で「これがいい」と思っても、実際に使ってみると合わないことも多いです。
8ヶ月以降、もしくは出産後に買い足せば十分間に合うので、ストックは最低限にしておきましょう。ネット通販やドラッグストアを活用すれば、必要なときにすぐ手に入ります。
私も「オムツは大量に買わなきゃ」と思っていたのですが、実際に使ってみると肌に合わず別メーカーに変更しました。最初から少量にしておいて大正解でしたね。
③ベビーカーやチャイルドシート
ベビーカーやチャイルドシートなどの大型アイテムは、必須ではあるものの、急いで7ヶ月で揃える必要はありません。特にベビーカーは実際に赤ちゃんと一緒に試してから選んだ方が失敗が少ないアイテムです。
また、車を使う頻度や家の周辺環境によっても選ぶべきタイプが変わります。普段から車移動が多いならチャイルドシートを優先すべきですが、ベビーカーは退院後すぐに必ず使うわけではないので、出産後に赤ちゃんの様子を見ながら選んでも遅くありません。
さらに、両親や友人からお下がりをもらえるケースも多いアイテムなので、慌てて購入せずに検討するのがおすすめです。私の知人も、出産後に「最新モデルがセールで安くなった」と聞いて、早まって買ったことを後悔していました。
7ヶ月では「どんな種類があるのか調べておく」くらいにとどめ、実際の購入は8ヶ月以降でも十分です。
④生活スタイルに合わせるもの
授乳ケープや抱っこ紐、搾乳機などは、家庭の生活スタイルや赤ちゃんの性格によって必要性が変わるアイテムです。7ヶ月で先走って揃えると「結局使わなかった」ということになりやすいので、後回しでも問題ありません。
例えば、外出が多い家庭なら授乳ケープや抱っこ紐は必須ですが、外出が少ない場合は出番がほとんどないこともあります。搾乳機も母乳の出具合によって必要性が大きく変わります。実際に出産してから生活に合わせて買い足す方が無駄になりません。
私も抱っこ紐は7ヶ月で買うか悩みましたが、実際に赤ちゃんが生まれてから「密着が好きな子だ」と分かってから購入しました。その結果、納得して選べたので良かったです。
生活スタイルや赤ちゃんの様子に合わせて、8ヶ月以降に購入を検討すれば十分に間に合いますよ。
先輩ママの体験談から学ぶ出産準備のタイミング
先輩ママの体験談から学ぶ出産準備のタイミングについて解説します。
リアルな体験談は、これから準備を始める方にとってとても参考になります。それぞれのケースを見ていきましょう。
①7ヶ月で準備を始めた声
「7ヶ月で準備を始めて良かった!」という声は非常に多いです。特に多かった意見が「体調が安定しているうちに買い物できたのが助かった」というものです。妊娠後期に入ると、腰痛や息切れで外出が大変になるため、7ヶ月で一通り揃えておいたことが結果的に大正解だったという感想が目立ちました。
また、7ヶ月から準備することで「セールを利用できた」「比較検討する時間があった」という声もあります。経済的にも心理的にも余裕を持って準備できたという意見は、これから準備する人にとっても大きなヒントになりますよね。
私も7ヶ月から準備を始めて、結果的に「もう準備は大体できている」という安心感を持ちながら後期を過ごせました。不安が減る分、リラックスして出産を迎えられるのは大きなメリットでしたね。
②遅めに準備して焦った声
一方で「準備を後回しにして後悔した」という声も少なくありません。特に9ヶ月や臨月に入ってから慌てて準備した人は「体が思うように動かなくて大変だった」「欲しい商品が売り切れていた」という経験をしています。
中には、急に切迫早産で入院になり「何も準備できていなかったから、家族に頼んで買いに行ってもらった」というエピソードもありました。欲しいブランドやアイテムがあっても、代わりに用意してもらうのは難しく、結果的に満足できない買い物になってしまうこともあるようです。
こうした声からも分かるように、準備を遅らせるリスクは意外と大きいです。早めに行動することで避けられるトラブルは多いんですよね。
③買ってよかったもの・不要だったもの
先輩ママの体験談でよく挙がるのが「買ってよかったもの」と「不要だったもの」です。例えば「授乳クッション」「ガーゼ」「肌着の多めのストック」などは買って良かったと感じる人が多いです。一方で「ベビー用の湯温計」「オシャレ着」「使わなかった哺乳瓶」などは不要だったという意見が目立ちました。
特に洋服に関しては「新生児用を大量に買ったけど、すぐサイズアウトして無駄になった」という声が圧倒的に多いです。逆に「肌着はたくさん用意して助かった」という声が多数派でした。
こうした体験談は「自分が何を優先して揃えるべきか」を考える良い材料になります。買って良かったものリストを参考にすれば、失敗の少ない準備ができますよ。
④パートナーとの協力エピソード
出産準備はママひとりで抱え込むのではなく、パートナーと協力して進めることでよりスムーズになります。先輩ママの体験談でも「夫と一緒に選んだことで楽しかった」「パパが率先して準備してくれて嬉しかった」という声が多くありました。
例えばベビーカーやチャイルドシートはパパの意見も取り入れながら決めた方が、後から使いやすいことが多いです。また、準備を一緒にすることで「自分も父親になるんだ」という実感がパパに芽生えやすくなり、育児に積極的になってくれるケースも多いんですよね。
私の友人も「夫と一緒に出産準備をした時間が良い思い出になった」と話していました。単なる買い物ではなく、家族としての絆を深める時間になるのも出産準備の魅力だと思います。
まとめ|出産準備 7ヶ月は早すぎない安心のタイミング
| 出産準備は7ヶ月から始めても早くない? |
|---|
| ①7ヶ月は安定期後で動きやすい時期 |
| ②体調や入院リスクを考えると安心 |
| ③必要なグッズをじっくり選べる |
| ④夫婦で相談する余裕がある |
出産準備は7ヶ月から始めても早すぎることはありません。むしろ体調が安定していて動きやすく、比較検討やセールの利用もできる安心のタイミングです。
一方で、買いすぎや季節外れのアイテムを選んでしまうリスクもあるので「最低限を揃えて、あとは出産後や直前に買い足す」という柔軟さが大切です。
必需品は7ヶ月で揃え、ベビーカーや季節グッズなどは後回しでも間に合います。先輩ママの声からも、早めに準備することで安心感を持って出産に臨めたという体験談が多く聞かれました。
これから準備を進める方は、自分と赤ちゃんにとってベストなタイミングを見極めて、楽しみながら進めてみてくださいね。
関連情報はこちらも参考になります: 厚生労働省|妊娠・出産・子育て支援

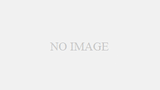
コメント